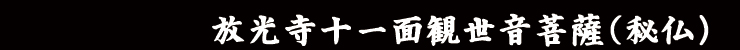|
|
|
|
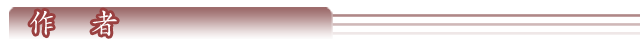 |
●聖徳太子作、行基が安置したという説。
あと行基作という説。平安時代後期の作者不詳という説。
|
●貞観風の趣を残すという
|
●昭和四十九年十一月十四日県宝に指定
|
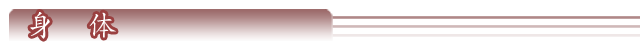 |
●等身大(164cm) 一本作り桂材でできている
|
●面幅(17.4cm) 面奥(21.5cm) 肱張(46cm) 裾張(37.2cm)
|
●彫眼、左手手首及び右手手先まで、本体と供木。左手手先から両足先は後補、頭上面は一面残してほかは後補。顔は彩色は後補、木心は左肩、下げ髪を結い、髪筋をあらわさない平彫りとし、両耳に髪二束を巻いている。
|
天衣をまとい、左手は肘を曲げ壷を持ち、右手は垂下し、掌を前にして第一・三・四指を捻じ、頭部をやや左に振り、腰を僅かに左に振って立っている。
|
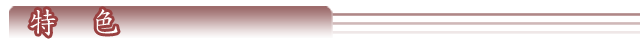 |
●像は肩幅のあるがっちりとした体形を示し、両膝の中央に渦文をきさんでおり、その一木造の古式技法は平安前期の一本彫成像に通ずるものがある。しかしながら面相の目鼻立ちや、着衣の彫りはかなり浅くなっており、体部の造型は肉身の抑揚が乏しくなり、量感も総じて減少し、平安時代の末期の作風が顕著に見られる。こうした、前代の影響をとどめる彫像は、全体をはたんなくまとめる手馴れた造型には見るべきものがある。
|
千三百年の間、幾多の風雪や法難に遇い傷みが激しく、後背、台座は後補のものである。そして長い年月のなかで、少しずつ顔などの部分に補修の跡がみられる。
|
|